ご相談・お見積もり無料!
089-904-5683
[電話受付時間]9:00~18:00 年中無休
24時間受付中
[受付]9:00~18:00 年中無休
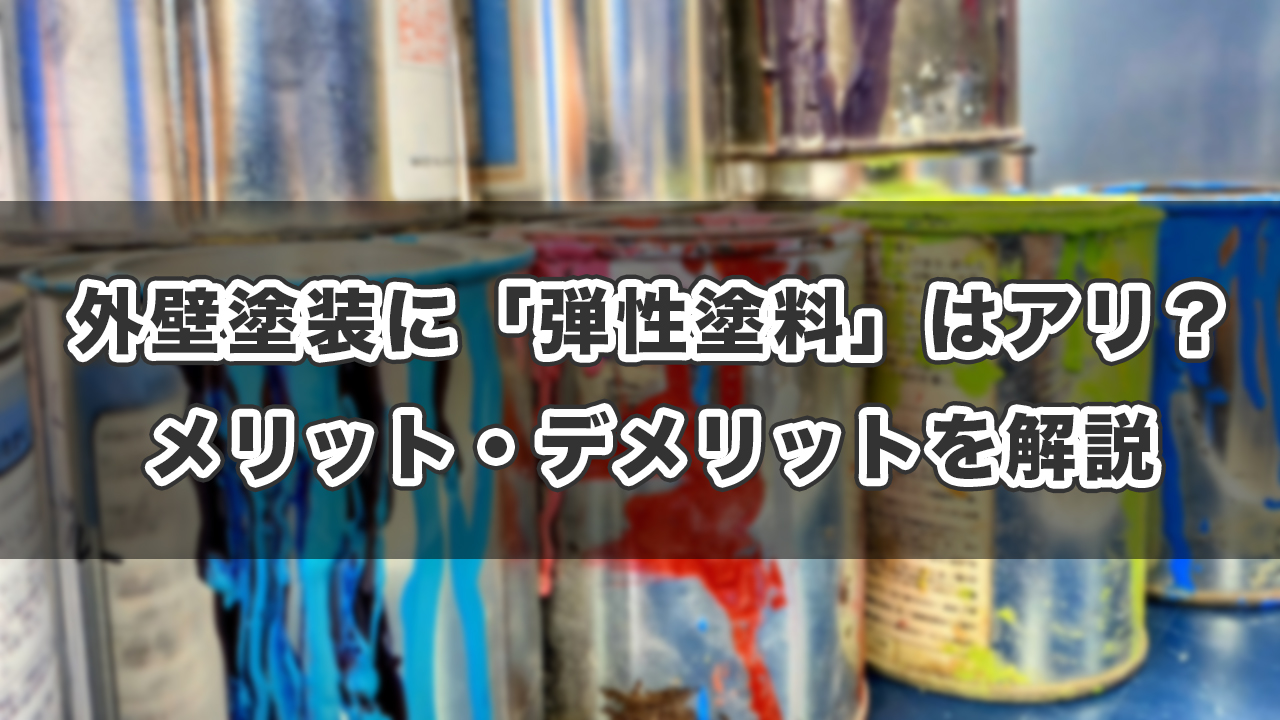
築年数が経過した家の外壁に、細かいひび割れが目立ち始めたら、塗料の種類にもこだわりたくなるものです。そんなとき候補に上がるのが「弾性塗料」です。伸縮性があり、ひび割れに強いとされる塗料ですが、建物の構造によって向き不向きがあるのをご存知でしょうか?また、導入前にメリット・デメリットも把握しておきたいものです。
そこでこの記事では、外壁塗装における弾性塗料について、メリット・デメリットを踏まえながら解説していきます。
外壁に生じるひび割れ対策として注目される弾性塗料。その基本的な性質から、硬質塗料との違い、どんな外壁材に向いているのかまで、詳しく解説していきます。
弾性塗料とは、乾燥後に20℃で伸び率120%以上という、ゴムのような伸縮性を持つ塗膜を作る塗料を指します。JIS規格でも明確に定義されており、可塑剤を配合することで硬化後も柔軟性を維持します。この特性により、建物に微細な動きやひびが生じても塗膜が追従するため、ひび割れを防ぎやすくなります。
防水性にも優れており、厚い塗膜が雨水侵入に強い構造を形成します。ただし、経年で弾性が徐々に低下し、8~12年ほどで効果が薄れる点には注意が必要です。
一般的な硬質塗料(シリコン塗料やフッ素塗料)に対し、弾性塗料はその名の通り「柔軟性」が最大の違いです。硬質塗料は乾燥後に硬化し、建物の微振動でひびが入ると塗膜が割れる恐れがあります。一方、弾性塗料は塗膜が伸縮することで亀裂に追随し割れにくいため、見た目や機能を長持ちさせる効果が期待できます。また、微弾性塗料(伸び率50~100%)と比べると、弾性塗料は明確に伸縮基準が高く、防水性や追随性にも優れています。
弾性塗料は、モルタル外壁やコンクリートなど、小さな亀裂が発生しやすい下地に非常に適しています。これらの外壁材は小さなひび割れが生じやすく、硬質塗料では割れが補えません。しかし、弾性塗料であれば塗膜が伸縮し追従するため、防水性能も保持しながら外観の劣化を抑えられます。また、施工方法にもいくつか種類があり、仕上がり厚さや耐用年数、コストに応じて選ぶことができます。
外壁塗装における「弾性塗料」の魅力は、ひび割れ対策だけでなく、様々な機能性が備わっている点にあります。以下では、そのメリットを5つのポイントに分けて、具体的な効果や理由をご紹介していきます。
弾性塗料はJIS規格で伸び率120%以上とされ、乾燥後にゴムのように伸縮する性質があります。
建物の動きによって生じる微細なひび割れにも塗膜がしなやかに追従するため、硬質塗料と違って割れにくいのが特徴です。特にモルタルやコンクリートといった、ひびが入りやすい外壁材に塗布するのが向いており、美観と防水性を同時に守る効果が期待できます。
ひび割れが進行する前に柔軟に対応できる点は大きなメリットと言えるでしょう。
弾性塗料は密着力のある厚い塗膜を形成するため、防水性能が非常に高いです。
水分が建物内部へ染み込む前に防御の役割を果たしてくれるため、建物のひび割れから雨水が侵入するのを防ぐほか、透湿性のある下地材との併用で塗膜の膨れも起こりにくくなります。雨の多い地域や風当たりの強い立地などでは、外壁からの水の侵入による構造劣化のリスクを大幅に軽減できるのがメリットとなります。
弾性塗料はひび割れが起こりにくくなるだけでなく、塗膜が厚いため経年劣化にも強く、美しい仕上がりを長期間維持しやすいです。紫外線や雨風による汚れ・変色・チョーキング現象を抑える効果もあり、メンテナンスの頻度を抑えることが可能になります。外観を常に清潔で美しく保ちたい方には、見た目の面でも優れた選択肢といえるでしょう。弾性塗料は初期コスト以上の満足度が得られるケースも多いです。
弾性塗料の中には、遮音性や遮熱性に優れた製品も存在します。厚い塗膜が雨音などの外部騒音を軽減し、室内での生活のストレスを和らげることができます。また、遮熱タイプでは特殊な顔料やセラミック成分を含むことで太陽光を反射し、夏の室温上昇を抑制する効果が期待できます。遮熱性能が向上すると、電気代の節約や冷暖房効率の向上にも繋がり、省エネ対策としても有効です。快適な住環境づくりを目指す方にとって、見逃せない機能の一つといえるでしょう。
建物は時間の経過と共に、温度差・湿度・地震・雨風の影響で絶えずわずかな動きを繰り返しています。硬質塗料では、これらの動きに追従できず、剥がれやクラックの原因になることもありますが、弾性塗料なら柔軟性があるため塗膜が割れにくく、下地の変形にしっかりと対応することが可能です。これにより、外壁の耐久性を高めながら長期的に建物を守る役割を果たしてくれます。
弾性塗料はひび割れや防水性に優れる一方で、特殊な特性ゆえにデメリット・注意点も多く存在します。以下では、弾性塗料を採用する前に知っておくべきデメリットや注意点を4つ挙げ、それぞれ解説していきます。
弾性塗料は塗膜が厚く密着性を重視しているため、通気性が低く湿気がこもりやすい性質があります。結果として、外壁内部に溜まった水分が塗膜の下に滞留し、「膨れ」や「剥がれ」を引き起こす可能性があります。特に日陰や風通しの悪い場所では、施工から数年後には浮き上がってくるリスクが高まります。
このようなトラブルを防ぐためには、透湿性のあるタイプを選ぶか乾燥環境を整える工夫が大切です。
弾性塗料は「通気工法」との相性に注意が必要です。
通気広報とは、外壁材と下地の間に空気層を設けて湿気を逃がす構造のことを指します。この工法では、壁の内部に湿気がこもらないよう適度な通気性が求められますが、弾性塗料はその気密性の高さから、空気や水蒸気の通り道を塞いでしまう可能性があります。そのため、サイディング外壁などの通気構造を持つ住宅に弾性塗料を使用すると、内部結露や塗膜の膨れ・剥がれといったトラブルに繋がることがあります。
密着力のある厚い塗膜を形成し、可塑剤や高機能成分を使用する弾性塗料は、他の塗料に比べて材料費自体が高く、施工工程も複数回にわたるため手間もかかります。そのため、外壁全体の工事費が数割程度高くなるケースも少なくありません。ただし、ひび割れ補修や再塗装の回数を減らせれば、結果的にプラスになる可能性もあります。耐久性とのバランスで検討する必要があるでしょう。
弾性塗料は、下地の状態によって仕上がりや耐久性が大きく変わります。高圧洗浄や十分な乾燥、適切なシーラー/フィラー選定などが曖昧だと、内部の湿気が放散されず「膨れ」「剥がれ」の原因になります。施工には熟練の技術が求められ、経験不足の業者による施工やDIYではトラブルが頻発します。他社の実績や事例の確認、透湿性仕様の確認など、慎重に判断する必要があります。
弾性塗料の適性は、住まいの構造によって大きく変わります。以下では「向いているケース・向いていないケース」を具体的に紹介し、事前に専門業者へ相談すべきポイントを詳細に解説します。
モルタル外壁は、乾燥時の伸縮や地震の振動などでひび割れが生じやすく、そこに雨水が侵入すると劣化に繋がります。弾性塗料は塗膜がゴムのように伸縮するため、そのひび割れにしなやかに追従し、防水性を保持しつつクラック(ひび割れや亀裂)を補う役割を果たします。
例えば「エラストコート」は最大伸び率250%で通気性を兼ね備え、モルタル特有の小さなひび割れから大きなひび割れまでカバーできる実績があります。
このように、ひび割れが目立つモルタル壁には弾性塗料が有効な選択肢です。
窯業系や金属系サイディングの中には「直貼り工法」で施工されているものがあり、通気層がない構造だと湿気がこもりやすく弾性塗料との相性が悪くなります。熱膨張による塗膜の膨れや剥がれが発生しやすく、膨張率の高い弾性塗料ではトラブルのリスクがより大きくなってしまいます。ただし、通気層付きの「通気工法」で施工されたサイディングであれば、通気性能を確保することで使用できるケースもあるため、業者に確認してみましょう。
塗料選びで失敗しないためには、事前の調査が必要不可欠です。まず、外壁材の種類(モルタル・サイディング・コンクリートなど)と施工方法(直貼り・通気)を確認してください。次に、クラックの有無・深度や湿気やすい場所の有無をチェックし、業者には「通気性のある弾性塗料や透湿機能の有無」「下地補修の方針」「塗装工法」などについて具体的に相談するようにしましょう。
「弾性塗料」と一口に言っても、フィラーとの使い分けや製品による性能差があります。以下では、微弾性フィラーとの違いや、主要メーカーの製品による違いを中心に解説していきます。
弾性塗料と微弾性フィラーは、伸び率と目的が異なる、似て非なる存在です。
JIS規格では、弾性塗料は20℃で伸び率120%以上、実際には200~400%に及ぶ製品も多く、ひび割れに強い性能が備わっています。一方、微弾性フィラーは明確な規格がないものの、伸び率50~100%程度で、主に下塗り材として使用されます。フィラーは表面の凹凸を埋めて滑らかにし、上塗りの密着性を高める目的で使用されます。
例えば、単層弾性工法では「シーラー」+「弾性塗料」を塗りますが、微弾性工法は下地にフィラー・上塗りに一般塗料を重ねます。この違いによって、仕上がりの弾性維持期間やコストも変わるため、目的や予算に応じて選びましょう。
市場には多くの弾性塗料があり、メーカーにより性能のアプローチが異なります。
例えば、オーストラリア発のアステックペイント「EC‑5000PCM」は圧倒的な伸び率600%超を誇り、防水・耐候・遮熱性に優れています。この高い弾性率が塗膜の柔軟性を長く保ちます。
日本のエスケー化研「セラミクリーン」は、防汚性・低汚染性を重視しており、ひび割れ防止と共に塗膜の清潔さを維持します。さらに、日本ペイントの「DANシリコンセラ」は塗膜が厚く防水に優れ、関西ペイントの「シリコンテックス」「アレスシルクウォール」は豊富なカラーバリエーションや耐候性を追求しています。
各製品の性能は「伸び率」「厚膜性」「耐候性」「遮熱性」「防汚性」などにより異なるため、住環境や目的に応じて比較・検討しましょう。
外壁塗装工事を成功させるためには「塗料選び」と「業者選び」が非常に大切になります。
以下では、塗料の性能や家の状態を見極め、信頼できる業者のポイントなどを詳細に解説していきます。
塗料にはそれぞれ特性があり、耐用年数や防水・遮熱性能などが異なります。塗料選びにおいて大切なのは「どの塗料が優れているか」ではなく、「自宅の状態や立地環境に合っているかどうか」を見極めることです。
例えば、日当たりが強い地域では紫外線に強い塗料、湿気がこもりやすい家では防カビ性の高い塗料が適しています。また、外壁の構造や素材との相性も重要視しましょう。自分で理解できるまで比較・検討することが後悔しないための第一歩となります。
優良業者は「この塗料はおすすめです」と言うだけでなく、「この塗料の注意点」や「他の選択肢との違い」もきちんと説明してくれます。例えば、高機能な塗料は価格が高い、施工が難しいといったデメリットがあることを伝えてくれます。このように詳細な説明を省く業者は、都合の良いことだけを伝えて契約を急がせる傾向にあるため注意が必要です。
後から「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、リスクも含めて誠実に情報提供してくれる業者を選びましょう。
業者選びでは「製品保証」と「施工実績」が仕上がりと安心感を左右します。優良な業者は、使用塗料メーカーの定める保証期間を明記し、さらに施工瑕疵に対応する独自の保証も提供しています。加えて、過去の施工事例やビフォーアフターの写真、利用者のレビューなどを確認することで信頼できる業者かどうか判断できます。また、アフターサービスの有無が明記されているかどうかも確認しましょう。
価格だけでなく、保証内容の有無と施工品質を総合的に見ることが、後悔しない選択に繋がります。
弾性塗料は、ひび割れへの追従性や高い防水性、遮音・遮熱効果など、多機能な特性を備えた塗料です。モルタル外壁のようなクロックが発生しやすい構造に適しており、柔軟な塗膜が微細な動きにも追従して建物を保護します。一方で、通気性が低く湿気がこもりやすいため、サイディングなど通気工法の外壁とは相性が悪い場合もあります。
弾性塗料を使用する際は、下地処理の丁寧さや施工技術が大切になるため、業者選びによって効果が大きく左右されます。業者を選ぶ際は、詳細まで説明してくれるかどうかに加え、製品保証や施工実績に問題がないか確認することが大切です。
